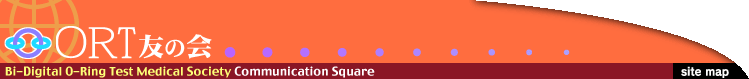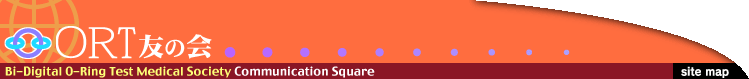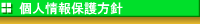 |
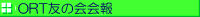
| 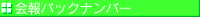 |
| ● |
友の会会報 NO.12
November,2006 |
| ● |
友の会会報 NO.11
November,2006 |
| ● |
友の会会報 NO.10
November,2005 |
| ● |
友の会会報 No.9
November,2004 |
| ● |
友の会会報 No.8
November,2004 |
| ● |
友の会会報 No.7
November,2003 |
| ● |
友の会会報 No.4
November,2002
|
| ● |
友の会会報No.3
November,2002 |
| ● |
友の会会報 No.2
November,2001
O-リングテスト時に生じるキャンセル現象
|
| ● |
友の会会報 創刊号
November11,2000
第4回国際シンポジウム |
|
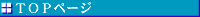 |
 |
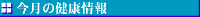 |
|
|
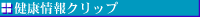 |
|
|
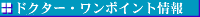 |
協会員医師による健康ワンポイント
今月の質問
「生理痛に対して針灸師として
どのような治療をされているか?」
|
|
|
|
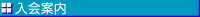 |
|
|
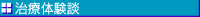 |
 |
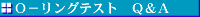 |
 |
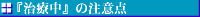 |
 |
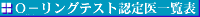 |
バイ・ディジタルO-リングテストに相当の知識と経験があり、実力があると認められた先生のリスト
|
|
 |
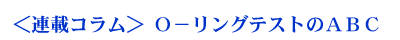 |
日本バイ・ディジタルO-リングテスト協会
副会長 下津浦康裕
下津浦内科医院 院長 久留米市東町496 TEL:0942-36-0620
|
身体に良いもの悪いもの 2005年1月14日
スマトラ島沖大地震後のインド洋大津波被害がトップニュースとして世界を駆けめぐる中、私はインドのカルカッタのホテルでこのお話を書いています。私は音楽評論家の湯川れい子さんやお坊さんの中村行明さんと共に孤児を集めたレインボーホームの慰問とインド洋大津波の救援物資を運ぶことを目的にこのインドにやって来ました。
信号で止まった我々の車に集まってくる人々の中には物乞いの人達に混じって災害の救援募金活動の人の姿もあります。今や、地震災害後にCNNニュースの伝える最大の関心時は死者15万人以上、家を無くした人50万人、孤児となった子供達150万人という数だけでなく、水や食衛生の悪くなった被災地に予想されるコレラや赤痢や腸チフス蔓延等による二次感染症災害です。
被災された人達に今ほどるバイデジタルO-リングテストによる食品チェックのやり方を教えたいと思ったことはありません。これまでもBSEやSARSや鳥インフルエンザ等による健康被害がトップニュースで世界に報じられたり、食中毒や農薬汚染や食品添加物が話題になるなど現代人の食生活環境は甚だ危険に満ちあふれています。しかも、現代では食品流通が高速一本化されている為その被害は同時多発性に発生する特徴を持っています。
ここインドではゴミを漁る牛や犬の姿をよく目にします。彼等はどの様にして食べられる物と食べられない物を見極めて生きているのでしょうか。私は以前、河豚で有名な料亭のご主人の次のような話を聞いたことがあります。ご主人は毎日のように仕事が終わるとポリバケツに魚の臓物や生ゴミを入れてゴミ回収に出すのですが一年を通じて毎日のように犬や猫にひっくり返され食べられてしまうそうです。しかし、河豚の出回る寒い時期になるとあたかも毒が入っていることを知らされているかの如く犬や猫はそういった行動をしなくなるのだそうです。
それで魚を日持ちさせるため魚をビニールに入れ河豚の毒を塗って外に置いておくのだそうです。もし、犬や猫が食べる前に動物的本能で食べるものの善し悪しを判断しているとすればこれはすばらしい能力といわざるを得ません。このような能力は動物が健康に生きるための必要欠くべからざる危険回避の能力ではないかと思われます。
私たち人間にも同じように今から口にしようとする食品が身体に良いか悪いか食べる前にわかる能力はないものでしょうか。実は、私はステーキが食べたくて専門店に出かけた筈なのに出されたステーキを見て余り食べたくないと感じてしまうときがあるのです。何故そう感じたのか説明しろと言われても説明できません。何となく第六感で感じてしまうのです。食べたくないと感じるのも危険回避の能力かもしれません。
今回の大地震後のインド洋大津波で人間は十万人以上が亡くなりました。しかし、動物は山へ逃げ一匹も死ななかったという報道が成されています。このお話も動物の危険回避の能力でしょうか。人間だけが死ぬということは人間は危険回避の能力が低下してきている事が考えられます。人間にも危険回避の能力がありその能力を目に見える形にするのがバイデジタルO-リングテストではないかと思われます。
実際のやり方をご説明しましょう。今から食べようとする食品がその人に良いか悪いか調べたい時には、片方の手の平に調べようとする物を乗せるか人差し指で指さして、もう一方の手の指でO-リングの形をした指の輪(O-リング指)を作って別の人にそのO-リング指を左右に引いてもらいます。O-リング指の輪が開くか開かないかで筋力低下を調べます。O-リング指が開くものを(-)と評価し、開かないものを(+)と評価します。
身体に良いものであれば指の筋力は強くなりO-リングの輪はしっかり閉じているのです。しかし、身体に悪い物であれば指の筋力は弱くなりO-リングの輪は弱くなり指の輪が簡単に開いてしまうのです。これがバイデジタルO-リングテストによる食品チェックのやり方です。このテストは人間の感性に根ざした生理的現象で私たちが今から口にしようとする食品が身体に良いか悪いかを食べる前に判断できる方法でもあるのです。今から食べようとしているものを持ったり、指さしてO-リングテスト(-)のものは食べないようにしましょう。
こうすることで身体に害のある食品を食べる危険は甚だ少なくなります。ただし、安全であることが解っていてもO-リングテスト(-)の結果になることがあります。そのときは量が多すぎないか考えてみましょう。例えば、ビールを徐々に量を増やしてO-リングテストで調べるとビール200mlまではO-リングテスト(+)でもその量を少しでも超えるとO-リングテスト(-)になってしまうことがあります。これはビール200mlまでは健康に飲めてもその量を少しでも超えると飲み過ぎになる危険を教えてくれているのです。
このように、身体に悪いものだけでなく、砂糖のように身体に良いものであっても、糖尿病の人にとっては量的に悪い場合もあるのです。その人の健康状態に応じて、食べようとするものの適切な量が解れば、健康を害するほどたくさんの量を食べることを避けることができるためにその人の健康維持にとても役立つものと思われます。
ごく稀にこの原則が当てはまらないことがあります。それは食べたものが胃に残っている間に同じものをO-リングテストで調べたときです。例えば、みそ汁を食べて1~2時間以内に同じみそを手に持たせO-リングテストで調べると、食べたみそがその人の体内にあるために、本当は身体にいいみそであっても反応(共鳴現象)を起こして、O-リングテスト(-)の結果がでてO-リング指が開くことがあります。本当は身体にいいみそを、身体に悪いと間違って判断してしまうことがあるのです。共鳴現象についての正しい理解については別の項に譲りますが、食べて直ぐに食べた物と同じものをテストするときは注意してください。
我々が食べようとする食品が身体に悪い物質に汚染されていないか自分の健康を損なう恐れがないかなどを見極めることは困難です。この地球に生きる多くの人たちがバイデジタルO-リングテストによる食品チェックのやり方を身につければ食生活から健康を害することは少なくなり、その人々の瞳は健康な色に輝くでしょう。
バイデジタルO-リングテストによる食品チェックを学ぶことで健康な食生活が実践出来るものと思われます。特に大地震災害に晒されているここインド洋諸国では二次感染症災害を回避する方法としても是非このテストを利用して頂きたいものです。
|
| |
|